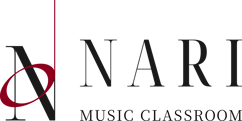とても、とても暑いですね。
溶けてしまいそうに暑い中、レッスンに来てくれている生徒さんたち、本当にありがとうございます。
7月にあるピアノ検定試験に向けて特訓中です
発表会に出演しなかった生徒さんたちを含め、数名の人たちはアメリカのギルドピアノ検定試験に向けてレッスンに励んでいます。
自由曲での検定試験になるので、発表会の曲をそのまま試験曲にする生徒さんもいますし、曲を変更して受験する生徒さんもいます。
発表会には出演しなかったけれども、こちらのピアノ検定には受験する生徒さんもいます。
「自分の意志で行動をしてもらう」という我が教室のポリシーが反映しているようにも感じています。
ピアノを演奏する以上、なんらかの形で人前での演奏は必須のように考えているので、密かに検定を受けるようプッシュしていることが伝わっているのかもしれませんが……。
検定を受ける人の中で、ピアノのレッスン中に私が不安定さを感じていた6年生の生徒さん。
発表会は、自身がリーダーとなっているクラブの試合の日程とかぶるため、出演は辞退していました。
ですが、検定は動画審査もあるため、受けてみようとお母さまとも話をして勧めたところ、本人もしぶしぶながら「やってみてもいいよ」ということになりました。
課題曲を自分自身で決め(課題曲は指定されておらず、私も指定しません)レッスンを始めたところ、今までとは違う前向きな姿勢が見られ、音読みだけでなく、テンポアップも、ダイナミクスも考えられる演奏が出来てきて、お母さまからのLINEで、「ピアノが楽しいと言ってます」との返信が……♥
もともと、コツコツとまじめに取り組む感じでレッスンをしていた生徒さんですが、最近では少しの注意で涙が出たり、うつむいたままお話しもしないでレッスンをしたり、難しいお年頃になっていました。
今回、課題曲に選んだソナチネが、古典のかわいらしい曲で、構成もわかりやすく、楽曲のいろいろな話をしながら勧めたところ、弾きやすく感じた様子でした。
おうちでしっかりと楽譜を読み取って弾いてきたのをほめたところ、ノリノリになったようで、今では、クオリティを上げるためにどうしたらいいと思う?という話をレッスンで出来るようになっています。
子ども用のレッスン教材は何を選ぶべきか?
従来のレッスンでは今の子どもたちに合わないのではないか……と思い、新しい教材を取り入れてレッスンをしていました。
それが良い場合もありますが、この生徒さんのように、新しい教材でつまずいた時に、昔の教材、いわゆるクラシックなものを取り入れることで、本来の音楽の良さが伝わるような気がしています。
実際、単純な和音進行(シンプルな構成)を弾きやすいと思った生徒さんが楽しさに気づいたように、音楽の本質は案外シンプルだと思います。
上っ面だけを演奏するのではなく、根本から理解して、少しずつ難しいこと、ややこしいことにチャレンジしていくのが、本来のレッスンであり、小さな生徒さんたちを指導していくうえで大切なことだと、改めて思っています。
近い将来に自宅でピアノ教室を……と考えている大人の生徒さんが、子どもたちの教材の多さに「何を選んでいいかわからない」と訴えてこられたこともありました。
本当に今は見た目がカラフルで(昔の教材はけっこう渋い)いろいろな教材があります。
ありますが、実際に使えるものは本当にわずかで、その見極めが難しい……。
何が難しいかというと、生徒さんたちの個性がさまざまで(それが面白いのですが)同じ教材でもどのように使うかは生徒さん次第なのです。
その生徒さんにあわせて、ある教材からどのように幅をもたせていくか(ふくらませていけるか……)それが出来るかどうかが、とても大事なことだと思います。
現在、私の教室では、導入では全音さんのピアノアドヴェンチャーファーストを使っています。
そこから、音楽の基礎知識を楽しくリズミカルに指導して、音楽史まで広げていきます。
その後、生徒さんによりけりですが、古典のバイエル(抜粋)、ブルグミュラー、ソナチネから、バッハ、ツェルニー、モシュコフスキーもろもろを、レッスンでさら〜っと弾いていきます。
バイエルをさら〜っと終える生徒さんは、古典ものの曲を難なく弾き、正確に楽譜を読みます。
バイエルから進めていくことで、自然と曲の流れが身につくように思います。
(先生によっては、バイエルをこき下ろしている人もいますが……。)
エチュードとしてバイエルが物足りないと考えられる場合、先生側がプラスアルファで作曲するといいかと思います。
バイエルという教本は単純なだけに付け加えやすいので、生徒にあわせたオリジナルなエチュードにできます。
それが、生徒たちの即興演奏や初見演奏の力をつける手助けになったりします。
このレッスンは、いつも笑いがたえなくて、こちらも必死になるので、とてもとても充実した楽しいレッスンになっています。
終わりに
また、このあたりのレッスンは、次回お伝えしようと思います。
今回も、長々と最後までお読みいただき、ありがとうございました。